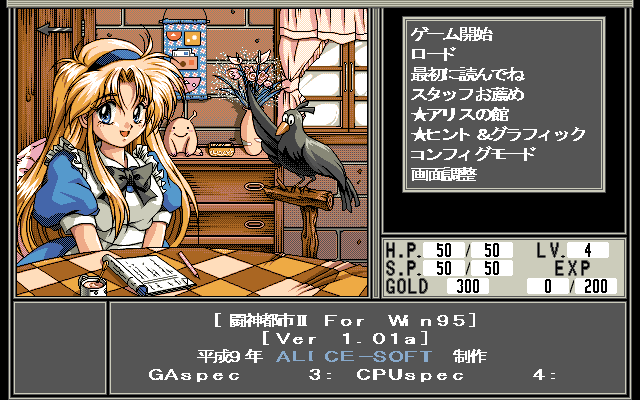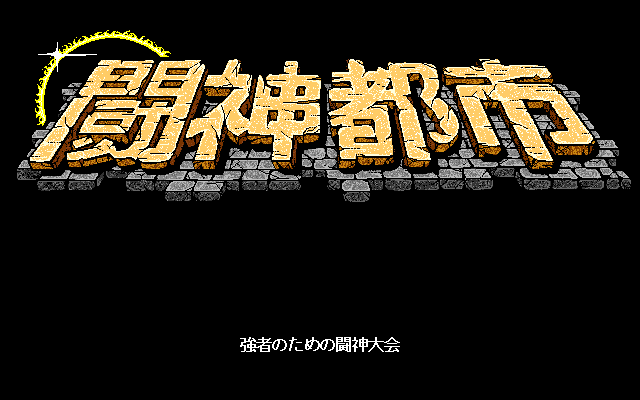今回は「大正時代」について調べてきたのでまとめていきたいと思います
この時代を選んだ理由はサムネにあるさくらの雲*スカアレットの恋と鬼滅の刃が同じ大正時代となっているからです
これらの作品に触れ、義務教育時代に全く歴史を学んでこなかった管理人がこの時代のことを知りたいと思い、それなりにこの時代について調べてきたのでそれらを記述していこうと思います
大正時代の概要
大正時代は明治時代の後、昭和時代の前に位置し
1912年7/30~1926年/12/25までの15年と日本史で現在一番短い時代区分となっています
この時代では第一次世界大戦という世界規模の戦争や、二度に渡る護憲運動、民主主義の発展などを掲げた思想やその運動を示す大正デモクラシーや、食事、服装などの近代化など短い時代ながもかなり激動の時代となっています
ちなみに大正時代が短い理由は大正天皇は元々体が弱く病弱であったためです。
そのため後半になると政務が行うことができず息子(後の昭和天皇)が摂政となり政務を行ってました
大正時代で起きた主な出来事
1912-1913年 第一次護憲運動
護憲運動とは、各種の民主主義的な活動がされた2度起きた代表的な運動で、
特に第一次護憲運動は大正デモクラシーの出発点として位置づけられる重要な運動となります。
昔は憲政擁護運動とも呼ばれていました。
この活動が起こった背景から説明するととても長くなってしまうので要点のみまとめて説明すると、
当時権力を持って好き勝手に政治をしようとしていた長州藩、薩摩藩出身者に対して人々が不満を感じていたこと、その出身者の桂太郎が内閣を組閣したことやその活動によって民衆が暴動を起こす騒ぎになったことで内閣を降りることになりました。
またこの中で憲政擁護会が発足され、「憲政擁護、閥族打破」を掲げて当時長州藩、薩摩藩と癒着があった陸軍に対しての反陸軍運動を起こしこれが第一次護憲運動となります
1914年-1918年 第一次世界大戦(WW1)
戦争が起きた背景やその内容は個々に調べていただくとして結果的に日本はロシアに向けて「シベリア出兵」をすることになることと、それに付随しておきた尼港事件に巻き込まれます
ただこの戦争によって日本は造船業などを通して大きな利益を生むことができ好景気になります
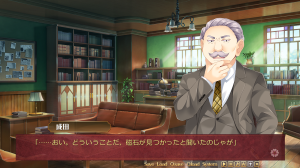
ナリゴンも造船業で富豪になった人物でしたね
1918年-1922年 シベリア出兵
WW1で日本はアメリカの呼びかけによって共同出兵をすることになりました。
その目的は「チェコ軍団救援」「ロシア内政不干渉」とするものでしたが、チェコはロシアと戦闘状態にあったためにロシアに干渉しなくてはならないこと、1918年にドイツ軍と連合国軍との間に休戦協定が成立し1919年にはベルサイユ条約によってドイツは海外植民地を失いチェコが独立しました。
なのでアメリカ、日本のシベリア出兵は上記の目的と矛盾した上で出兵することになるのですが、後に日本軍がロシアの領土を占領していったことで他国から疑惑の目を向けられることになります
1918年 米騒動

サクレットではこの米騒動を加藤大尉が収めたとして彼が畏怖される要因のひとつになってますね。
シベリア出兵に日本軍が駆り出されることが分かったときに、米の需要拡大を見込んだ商人が米を買い占め、売り惜しみが発生し米価格が高騰した。
その中、富山県で発生した米問屋と住民の騒動が全国に広がり、米問屋の打ちこわしや焼き討ちなどが頻発した騒動のことを言います。
コロナが流行ったときもトイレットペーパーを買い占めて高額で売る人が多くみられましたね。
同じことをこの時代にやったらその人の家は放火されてたかもしれませんwww
1918年 初の平民出身の総理大臣の誕生
米騒動の後、日本で初の政党内閣の原内閣が誕生しました。
爵位を持たなく、平民である原敬(はらたかし)が首相となります。
しかし1921年、原敬は東京駅で、駅員の中岡良一によって殺害されてしまいます。

サクレットでもこの事件名は出てきましたね。
(上記画像はかなり重要なネタバレが含まれるため右半分は強めのモザイクをかけています)
1920年 尼港事件(にこうじけん)

サクレットではこれから起こることがらとして主人公の司君が説明している描写があります。
一言で説明すると日本がシベリア出兵でロシア領土を占領していたため赤軍パルチザン(ロシアなどの非正規軍などの武装集団)によってニコラエフスク(日本人はここを尼港と呼んでいた)にいた日本軍と日本駐留者が皆殺しにされ、そのに住む住民も総人口の半分ほど虐殺されてしまった事件
1923年 関東大震災
1923/9/1に発生
死者、行方不明者は約10万人以上を超える
神奈川、東京を中心に茨木、千葉、静岡東部までの内陸、沿岸に及ぶ範囲に甚大な被害をもたらした地震。
東京市内の約6割の家屋が被害にあった。
これもサクレットでは物語に関係する重要な出来事のひとつになってますね
1924年 第二次護憲運動
これも背景がなかなかややこしいので簡潔に記述してきます。
WW1によって世界的に民主主義的な政治運動が拡大してました。
日本でも「普選運動」が学生を中心に活性化してました。
1924年に清浦圭吾が内閣を設立しました。
当時は政党政治の流れが一時後退し非政党系内閣が続いていたこと、この清浦内閣は貴族院議員を中心に組閣されており「超然内閣」となっていました。
(ようは勝手に政治をやりますという組織が生まれてしまった)
これに「護憲三派」が結成されこの清浦内閣を倒すために第二次護憲運動が始まります。
結果的にこの護憲三派が衆議院議員選挙で勝利を収め、清浦内閣じゃ総辞職することになります
1925年 普通選挙成立


これまでの選挙は「制限選挙」と呼ばれ、制限される項目が多く納税によっても制限がありました。
しかし「普通選挙法」によって多くの制限が取り払われ、より多くの人が選挙権を持つことが可能となりました。
しかしこの時はまだ成人女性の選挙権は認められませんでした。
大正デモクラシー
明治維新によって日本は急速に近代化していきました。
政治についても江戸時代までの身分制度は撤廃され、民衆は全て平等に扱われるようになりました。
しかしそれでも権力は天皇や政府に集中してました。
それに不満を感じた民衆が民主主義運動や普通選挙運動(普選運動)で、政治は天皇や一部の政治家だけでなくみんなで話あって決めるべきという動きが起きます
この政治、社会、また文化などにおける民主主義の発展や自由主義的な運動、風潮、思想の総称を
大正デモクラシーと言います
大正時代の文化、暮らし
家族体系の変化
今まで家族の在り方については複数世帯が一緒に暮らすのが一般的でした。
これが大正時代に入ると都市部より両親と子供だけで暮らす核家族が主流になっていきます
女性の社会進出
大正時代では女性の社会進出も活発になっていきました。
家族みな共働きという体系からサラリーマンが増えたことで専業主婦という女性の在り方も増えた一方で女性がキャリアを積む仕事に就く社会進出も活発になっていった時代でもあります
それまで女性の職業は、女医や看護師、教師などの専門職に限定さrていましたが、
美容院や店員、事務職やタイピストなどのサービス業が新しい職業として出現してくるようになりました。
ちなみにタイピストは、文の代筆を行ったりする他にも、誤字の修正をしたり多言語の翻訳を担ったりしていたようです。今のようにネットがないので翻訳などについてはかなり大変であったと考えられます
服装、ファッション

女性の髪形は今までは束髪という日本と西洋の文化を取り入れた髪型が主流でしたが、ボブカットなどの髪を短くするショートカットの髪型も出現してきました。
また和装の女性は耳を出さない「耳隠し」が主流になったようです
また服装も従来の和装だけでなく洋服やハイヒールなどを身に着ける女性が出てきました。
それらは奇抜に見られながらも徐jに広がっていき「モダンガール」として憧れの対象になっていきました。
セーラー服もこのとき日本で初めて登場します

食事の変化



洋食は明治ころからもありましたが、大正時代になるとより浸透していき「カレー」「コロッケ」「とんかつ」が日本人の口に合うようにアレンジされたことと作りやすさも相まって「三大洋食」としてひろがっていきました。
しかしそれでも家庭での食事は和食が一般的でした。
(ごはん、味噌汁、漬物、豆、魚等)

またシベリアが生まれたのも大正時代とされています。
羊羹や小豆の餡子をカステラに挟み込んだお菓子。
現在はこのお菓子を作るために多種多様な食材が必要なことと制作工程に手間がかかるために製造者の数は減っていますが、昭和初期では「こども食べたいお菓子No1」になるほど親しまれていたようです。
ちなみにこのお菓子がなんで「シベリア」と呼ばれているのかは分からないようですw
その他
刀について

鬼滅の刃では鬼殺隊が刀を携帯していますが、大正時代でも人々は刀を持っていたのでしょうか?
答えはいいえです
1876年に廃刀令が出されます。
これによって軍人や警察が制服を着用する以外に刀を持つことは禁止されました。
なので炭治郎が所属する鬼殺隊は政府からしたら全員に違反者ということになりますww
「お金の価値について」 100円は大金だった!?
今ではほとんどなじみがなくなんならすでに使われていませんが日本にはお金の単位に「銭」というものがありました。
これは円に換算すると一銭=0.01円だそうです
またインフレが起こるまではお金の価値基準も現代と大分違います。
大正時代で100円というと現在でいう30~40万ほどになるようです
つまり昔の1円は現在の3000~4000円の価値ということですね
サクレットに出てくる10円札について


10円札は今まで8種類発行されていたようです。
サクレットで出てくる10円札は甲号券と呼ばれるものです。
右側に写っている人物は和気清麻呂という奈良時代末期から平安時代初期にかけて存在していた貴族で、
左の建物は護王神社で京都市の上京区にあるようです。
このお札は1899~1939年まで発行されていたようです。
まだまだ調べたことはあるので後日追記することもあるかと思います。
今まで私は、自分は今を生きているから昔を知る必要はないといい歴史の勉強を怠ってましたが、これらの作品を通して歴史に興味が出てきて勉強を始めてから、今の生活に通ずるものが昔から存在していたことを知り歴史を学ぶ面白さを知りました。
これらの作品はそういった意味で勉強への敷居を下げる良い作品であると思うことと、物語が面白い作品でもあるのでおすすめしたいですね
サクレットでは他にもいろんなワードが作中に出てきていたので気になって調べたものはまた別途記事にしたいと思います。
ではまた